はじめに
今回は令和6年度の試験に向けた勉強方法と、そこから学んだことについてまとめます。
令和6年度は社労士試験への初挑戦でした。
勉強期間は約半年間と短く、不合格を覚悟しての受験でしたが、結果以上に大きな学びを得ることができました。
使用した教材
- Studying(通信講座:講義+テキスト)
- 問題集(みんなが欲しかった!社労士合格のツボ 択一・選択)
- 模試(LEC・TAC)
勉強スケジュール(半年間の流れ)
2〜4月
- 平日は1〜2時間、休日は3〜5時間を確保
- Studyingの講義動画を労働基準法から視聴し、対応する問題を解く
- テキストの読み込みが足りず、問題演習中心の学習になっていた
5月〜8月
- 1日2〜3時間の学習を継続
- TACの一問一答と選択式対策に取り組む
- 模試を受験し、時間配分や長時間試験に慣れる
- 6月模試は「D判定」、7月は「C判定」
- この頃はStudyingもTAC問題集も中途半端になり、模試の復習まで手が回らなかった。
勉強時間の合計(概算)
半年間の合計は およそ400時間。
正確な記録は残していませんが、翌年の学習との比較に役立ちました。
初年度の試験勉強で学んだこと
基礎の重要性
社労士試験の合格のためには、いかに基礎を確実に理解・記憶できるかが最も重要だと感じました。
どれだけ勉強しても初見の問題は出題されます。しかしそれは他の受験者にとっても同じで、正答率が低い傾向があります。
だからこそ、正答率が高い問題を確実に取る=基礎力の充実 が重要です。
💡 テキストの読み返しと問題演習を繰り返すことが不可欠だと学びました。
教材の幅を広げすぎない
基礎を固めるためには、最初に選んだ教材を信じて何周もやり込むのが合格への近道です。
令和6年度の勉強ではStudying以外に手を出し、結果として全て中途半端になってしまいました。
💡 教材を増やすのではなく、まず1つをやり切ることの大切さを実感しました。
合格を意識して取り組む大切さ
2月開始という短期間での挑戦で「間に合わないかも」と不安はありましたが、必ず令和6年度で合格する という気持ちを持って勉強を続けました。
結果は不合格でしたが、この姿勢が「弱点の把握」や「基礎固めの重要性」に気づかせてくれました。
次年度の勉強でも「これ見覚えある」と思えることが増え、理解の深化につながったのはこの挑戦があったからだと思います。
💡 期間が短くても、直近試験に合わせて勉強することは大きな意味があると感じました。
まとめ
短期間でも「基礎固めが重要と認識できたこと」が最大の収穫でした。
この経験を踏まえて翌年度は「1年計画」で勉強を継続し、着実に力を積み上げる方針に切り替えました。
次回は、令和7年度の勉強スケジュール(労働法系科目の記録)をまとめます。
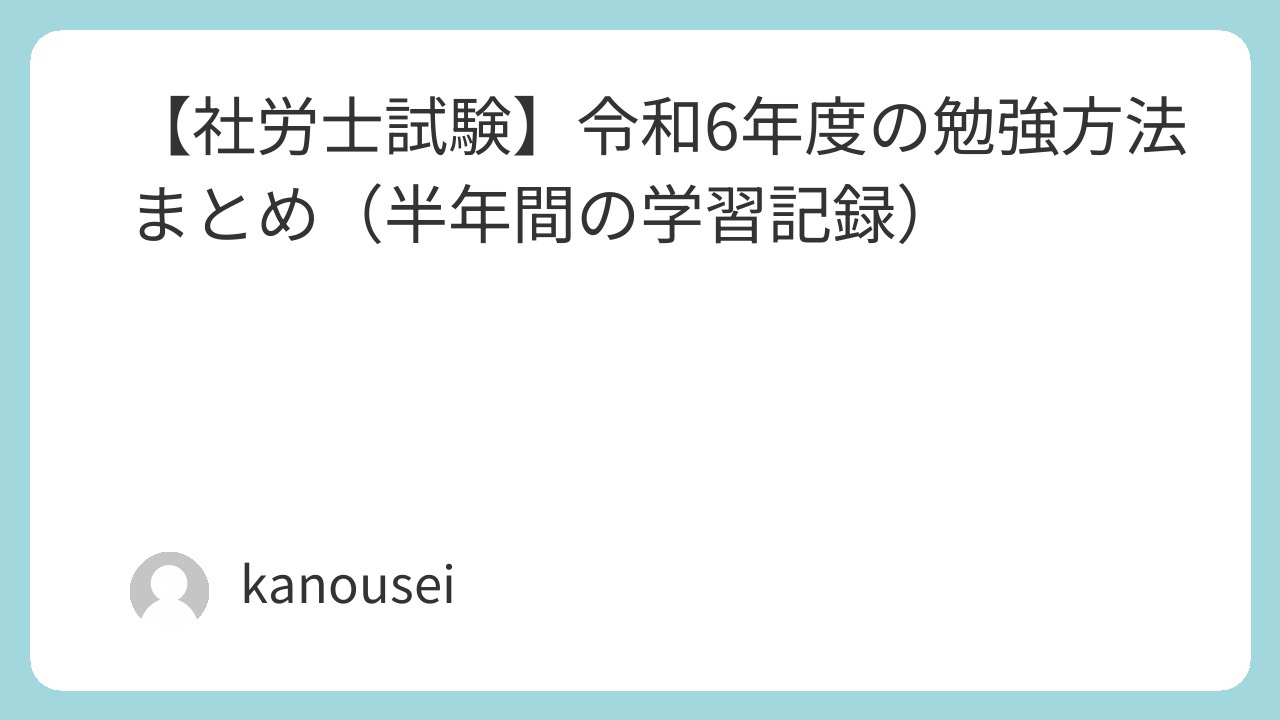
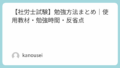
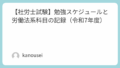
コメント