はじめに
社労士試験には「補正(救済措置)」と呼ばれる制度があります。
基準点に満たない受験者が多い場合、各科目の合格基準点が引き下げられることがあり、この補正により救われる受験生も少なくありません。
今回は、私自身の令和7年度の自己採点を踏まえつつ、補正が入りそうな科目を整理してみました。
補正(救済措置)とは?
以下、厚生労働省からの引用です。
各科目の合格基準点(選択式3点、択一式4点)以上の受験者の占める割合が5割に満
たない場合は、合格基準点を引き下げ補正する。
ただし、次の場合は、試験の水準維持を考慮し、原則として引き下げを行わないことと
する。
ⅰ) 引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合
ⅱ) 引き下げ補正した合格基準点が、選択式で0点、択一式で2点以下となる場合
出典:社会保険労務士試験の合格基準の考え方について
例えば、令和6年度の選択式の「労一」が2点に補正されました。
補正が入りそうな科目とその印象
予備校の講評や私の感覚をもとに、補正の可能性がある科目を挙げます。
選択式
労災
A,Bは少し細かいところからの出題かなと思いました。Cの長期家族介護者援護金という制度は私は初見で、完全に勘で解答して間違えました。D,Eは最高裁判例からの出題で自信をもって解答できた方は少ないのではないかなと思います。
労一
A,Bに入る得る選択肢が8つあったことから、難易度が高く、普段から情報にどれだけアンテナを張っているかという一般常識の色が強い設問かなと感じました。また、D,Eも判例からの出題で、Dの空欄の多さに面食らってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
社一
Aは、LECの公開模試が的中しており、LECの模試を受けた方は、正解できたのではないでしょうか。LECの成績表を見ても、8割以上が正解しておりました。Eは正解が「資産所得倍増プラン」という、こちらも情報感度がある程度ないと難しい問題ではないかと思います。
択一式
雇用・徴収
問7の解雇の効力など、細かいところから出題されている印象でした。今回の本試験の中では、この科目は4点確保して、他の科目で点数を稼がなければいけないと試験中に思いました。
健保
問題分のボリュームがあり、最も体力を消耗した科目でした。労基から解き始めた方は、ちょうど集中が切れるタイミングと重なり、さらに難しく感じたのではないでしょうか。
私の自己採点と照らし合わせて
自己採点では社一が2点でした。基準点(3点)に届かなかったため、補正が入るかどうかで合否が大きく変わります。なので、今回私は社一の補正に期待しています!
補正が入れば一気に合格ラインが変わる可能性があるので、発表日まで落ち着かない気持ちです。。。
私自身の自己採点結果については、こちらの記事にまとめています。
👉 【社労士試験】令和6年度・7年度 自己採点結果と振り返り
補正の可能性まとめ
最終的にどうなるかは試験センターの発表を待つしかありませんが、過去の事例から考えると今年も1~2科目は補正が行われる可能性が高いと考えています。
今回の補正予想に関連して、私がこれまで取り組んできた勉強方法や教材についても記事にしています。
👉 【社労士試験】勉強方法まとめ|使用教材・勉強時間・反省点
まとめ
- 令和7年度は「社会保険一般常識」を中心に、補正の可能性が高い
- 発表までは不安ですが、最後まで可能性を信じて待ちましょう
科目ごとの勉強スケジュールや労働法系科目の学習記録はこちらにまとめています。
👉 【社労士試験】勉強スケジュールと労働法系科目の記録(令和7年度)
📌 次回は「教材レビュー編」として、Studyingやアガルートなど実際に使った教材の感想をまとめます!
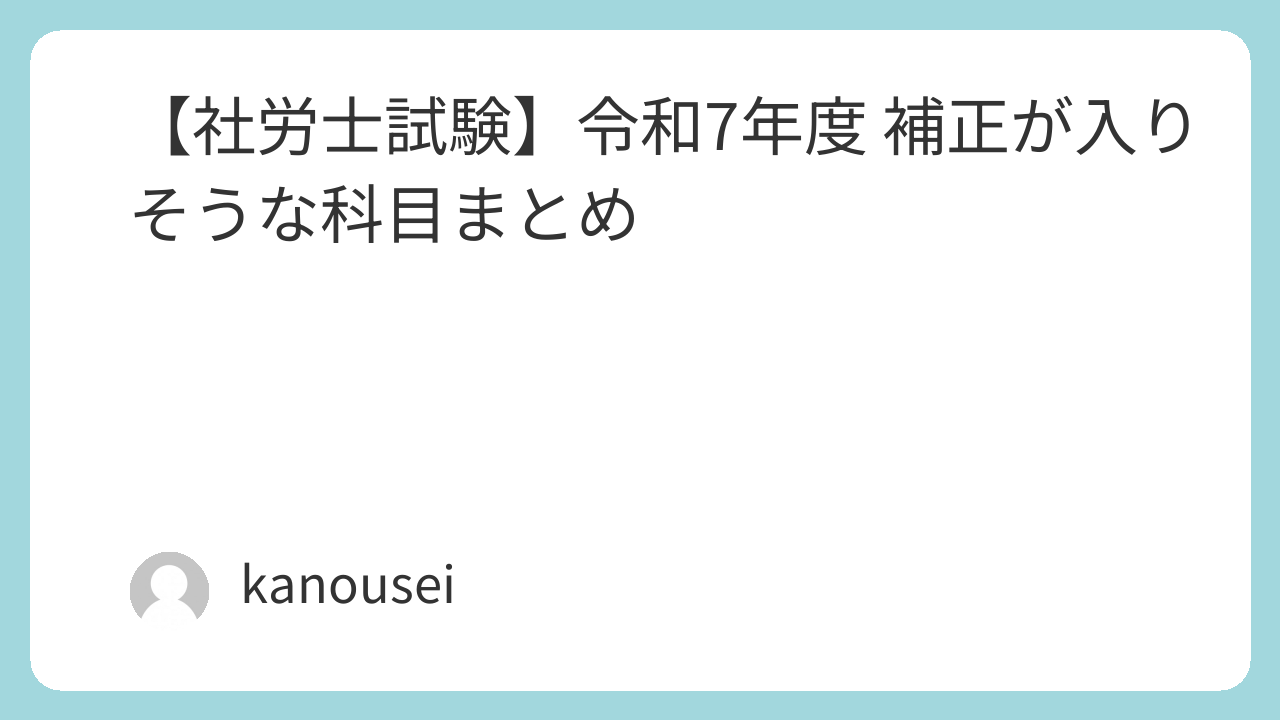
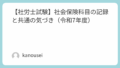
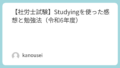
コメント