はじめに
今回は、令和6年度の試験で利用した Studying(スタディング) についてまとめます。
短期間(約半年)で挑戦したときのメイン教材として使い、実際に感じたメリット・デメリットを整理しました。
Studyingを選んだ理由
- スマホやPCで学習できる手軽さ
- 価格が他の通信講座に比べて安かった
- 初学者でも始めやすい講義とテキストが揃っていた
📌 「価格を抑えて学習できる」という点がStudyingを選んだ大きな理由でした。
実際の使い方
- 平日は通勤時間に講義動画の聞き流しや昼休みに講義動画を視聴
- 夜はテキストに対応した一問一答で演習
- 休日はまとまった時間で問題演習
💡 「動画で学ぶ→すぐに問題を解く」サイクルがシンプルで、初学者でも勉強を続けやすかったです。
Studyingのメリット
- スキマ時間を活用できる
→ スマホでどこでも勉強できた - 講義がコンパクト
→ 短時間で効率よく進められる - コストパフォーマンスが高い
→ 受講料が比較的安く、始めやすかった
他社では10~20万円が相場だが、Studyingは10万円かからない - テキストの図解がわかりやすい
→法律を初めて学ぶ人は、条文だけではなかなか理解が難しいが、
Studyingではテキストにスライドが適宜挿入されており、わかりやすかった - 白書・統計対策の講義が充実
→対策が難しい白書・統計について講義動画が充実している
次回以降比較するアガルートと比較しても、充実しており、かつ分かりやすく苦手意識を持 つことなく試験を迎えられた - 学習の進捗がわかりやすい
→試験本番までの逆算がしやすかった
💡個人的には4番目「テキストの図解がわかりやすい」が一番のメリットに感じました。
Studyingのデメリット
- 図解されたスライドを落とし込む必要性がある
→デメリットと言っていいのか迷うものではあるが、試験では文章で問われるため、Studyingのわかりやすいスライドでなんとなく理解したつもりだけでは、合格レベルには達しないと感じた
📌 短期間での基礎固めには十分でしたが、スライド図で理解したつもりになってしまいました。そのため試験本番では、初見の問題を理解するのに時間がかかってしまいました。最終的にはテキストを読み込み、文章でしっかり理解しておくことが必要だと感じました。
令和6年度での成果と反省
- 半年間で一通り全科目に触れられた
- 基礎固めには役立った
- 本試験では「基礎不足」が大きな弱点として浮き彫りになった
💡 合格に届きませんでしたが、勉強習慣をつくるきっかけとして、また短期間で基礎固めをすることができました。次回以降紹介予定のアガルートではこの点は難しかったかなと思いました。理由は、テキストの情報量が多く、Studyingより読み込むのに時間がかかるためです。また講義動画だけ視聴しても内容が理解できる点もStudyingのほうが優れている点だと感じます。
まとめ
Studyingは、
- 「これから社労士試験を始める人」
- 「スキマ時間で効率的に学びたい人」
におすすめできる教材だと感じました。
以上のことからStudyingは、要点が非常に分かりやすくまとまっていて素晴らしい教材です。これは2年目勉強していてより強く思いました。
➡️ 次回は、令和7年度で利用した アガルート についてまとめます。
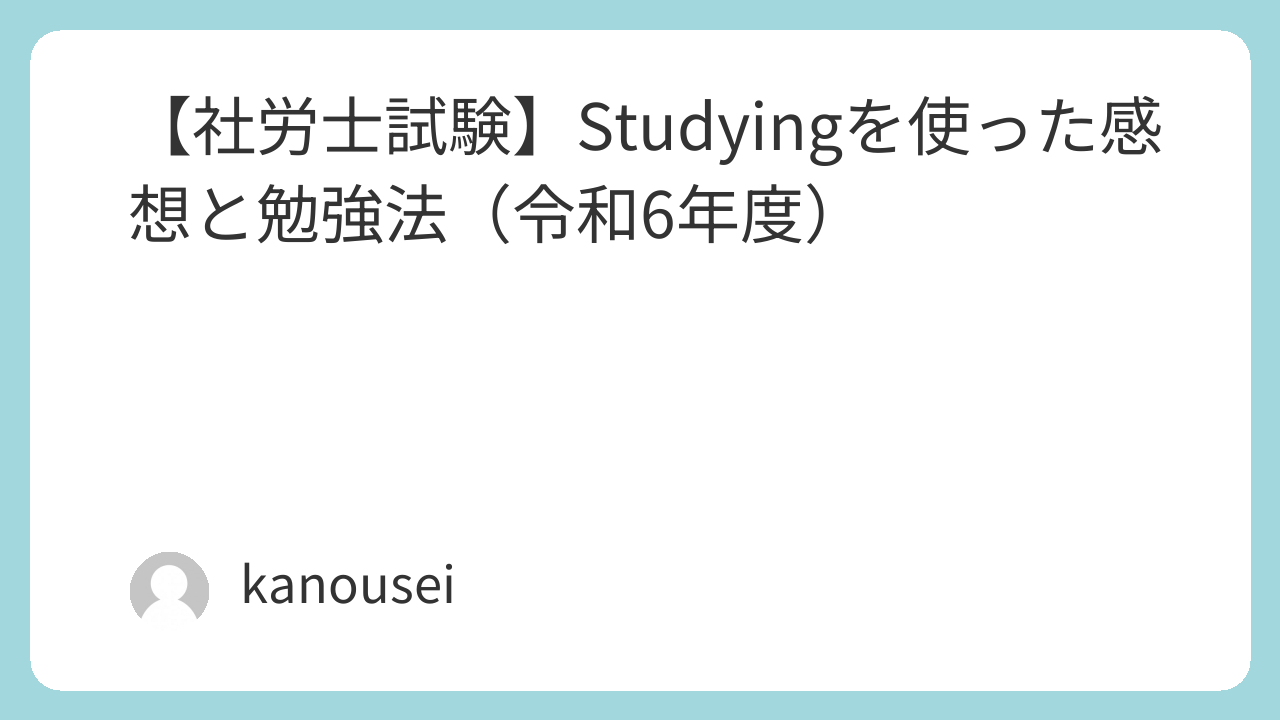
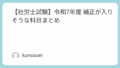
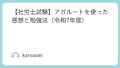
コメント