※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
こんにちは!
今回は、令和7年度の試験で利用した アガルート についてまとめます。
1年かけて勉強する中でのメイン教材として使い、実際に感じたメリット・デメリットを整理しました。
アガルートを選んだ理由
令和6年度試験の反省点
令和6年度の試験を終えての反省点は、「テキストの読み込みが足りない」ということでした。具体的には、問題集で出てきた論点は、解答できましたが、その他テキストの隅に書いてあったであろう論点は、そもそもテキストを全くと言っていいほど読んでいたなかったので、わからない問題がありすぎて試験中に頭が真っ白になってしまいました。
そこで、令和7年度に向けてやるべきことは、「テキストの読み込み」だと考えました。
通信講座の選定
具体的に検討した通信講座は「Studying」、「クレアール」、「アガルート」でした。それぞれ断念した理由は、以下の通りです。
- Studying:スマホやPCではなく、冊子で問題演習をしたかったため
- クレアール:合格点を目指す講座では少し不安に感じ、もう少し幅広く学習したかったため
なお、どちらも合格者を多数輩出している素晴らしい講座だと思います。ただ今回の自分の反省点を踏まえるとこれらではないという結論になりました。
また、大手予備校のTACやLECは近くに教室がないため、自習などで教室が使えることもなく、また令和6年度の模試のチラシを見て、オプション講座がたくさんありそうで、それらを受けると決して安くない受講料にさらにプラスでお金がかかりそうだと思い、断念しました。
令和7年度は、アガルートの中上級カリキュラムを受講しました。こちらは択一式30点以上取れている学習経験のある受験生の講座です。アガルートの講座は以下の特徴があります。
- テキストの本試験カバー率が90%と非常に網羅性が高い
- 中上級カリキュラムは10年分の過去問に加えて、択一式はそれ以前の過去問とオリジナル問題を合わせた問題集が付属しており、アウトプット強化に最適
- 合格して、特定の条件を満たせば、受講料のほぼ全額が返ってくる
令和7年度の択一式の点数からアガルートを選択したことは間違いではなかったと思っています。
👉【社労士試験】令和6年度・7年度 自己採点結果と振り返り
📌 「基礎を終えて本格的に得点力を伸ばしたい」という思いからアガルートを選びました。
アガルートのメリット
以下で2つのメリットをご紹介します。
テキストが圧倒的に詳しい
最初に労働基準法のテキストが届いたときは、その厚さに驚きました。それぞれのテキストが厚く情報量が非常に多いです。図も入っており、わかりやすくなっております。ただ、図はStudyingのほうがわかりやすく感じました。
| 科目 | テキストページ数 |
|---|---|
| 労働基準法 | 375 |
| 労働安全衛生法 | 187 |
| 労災保険法 | 230 |
| 雇用保険法 | 295 |
| 労働保険徴収法 | 168 |
| 労一 | 306 |
| 健康保険法 | 383 |
| 国民年金法 | 335 |
| 厚生年金保険法 | 352 |
| 社一 | 224 |
| 合計 | 2,855 |
テキストのボリュームがある分、読み込むのが大変で、テキスト読みの2~3回目までは、文章で理解するのに苦労した部分もありました。しかしその分実力が上がっているように感じました。
テキストのサイズは、B5サイズで持ち運んで通勤時間等に勉強するというよりは、机でしっかり読み込むのに適したサイズ感になります。
問題演習のボリュームが
10年分の過去問に加えて、オリジナル問題集のボリュームがあり、アウトプットに強いです。以下で問題演習のボリュームについて説明いたします。
アガルートでは、過去問10年分に加えてオリジナル問題集が用意されています。
実際に演習した問題数を科目ごとに整理すると、以下の通りです。
| 科目 | 択一過去問10年分 | 択一オリジナル問題集 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 294 | 261 | 555 |
| 労働安全衛生法 | 85 | 108 | 193 |
| 労災保険法 | 217 | 193 | 410 |
| 雇用保険法 | 259 | 219 | 478 |
| 労働保険徴収法 | 239 | 184 | 423 |
| 労一 | 179 | 113 | 292 |
| 健康保険法 | 431 | 337 | 768 |
| 国民年金法 | 433 | 302 | 735 |
| 厚生年金保険法 | 431 | 252 | 683 |
| 社一 | 260 | 167 | 427 |
| 合計 | 2,828 | 2,136 | 4,964 |
- 総計で約5,000問(4,964問)を解くことが可能です。
- 1科目あたり 500〜700問規模 の演習量が確保されており、十分なアウトプット練習になります。
- 特に 健康保険法・国民年金法・厚生年金法 の3科目はそれぞれ600問以上あり、社労士試験の得点源となる社会保険科目を徹底的に鍛えられます。
📌 感想:
「これだけのテキストのページ数、問題数を一つの講座内で網羅できるのは大きな魅力でした。インプット・アウトプット量が増加したことにより、大きな安心感につながりました。」
【PR】
アガルートの無料講座体験・詳細はこちらから
アガルート 社労士講座
アガルートのデメリット
- テキストの情報量が多い
→ 読み込むのに時間がかかり、短期間学習には不向き - 講義動画だけでは理解が難しい部分もある
→ テキストと併用することが前提になる - 価格はStudyingより高め
→ 受講料は20~30万円前後で、初学者には少しハードルが高い
例えば中上級カリキュラムフルで272,800円です。
💡 個人的には「しっかり勉強時間が取れない方は難しい」と感じた部分がありました。
令和7年度での成果と反省
- 択一式の安定感が増した
模試では一度も40点を切ることはありませんでした。(一番低くてTACの公開模試の44点) - Studyingと比べると「知識の厚み」は増したが、効率面では課題あり
まとめ
アガルートは、
- 「基礎を終えて、より深い学習をしたい人」
- 「情報量が多い教材で安心して勉強したい人」
におすすめできる教材です。
ただし、短期間で効率的に勉強するには向かず、時間と労力をかけてでも理解を深めたい人向けの講座だと感じました。
➡️ 次回は、Studyingとアガルートを比較して「どんな人に合うか」を整理した記事をまとめます。
- 豊富な講義動画とフルカラーテキスト
- 無料で講義体験も可能
- 合格特典も充実(合格時に全額返金キャンペーンなど)
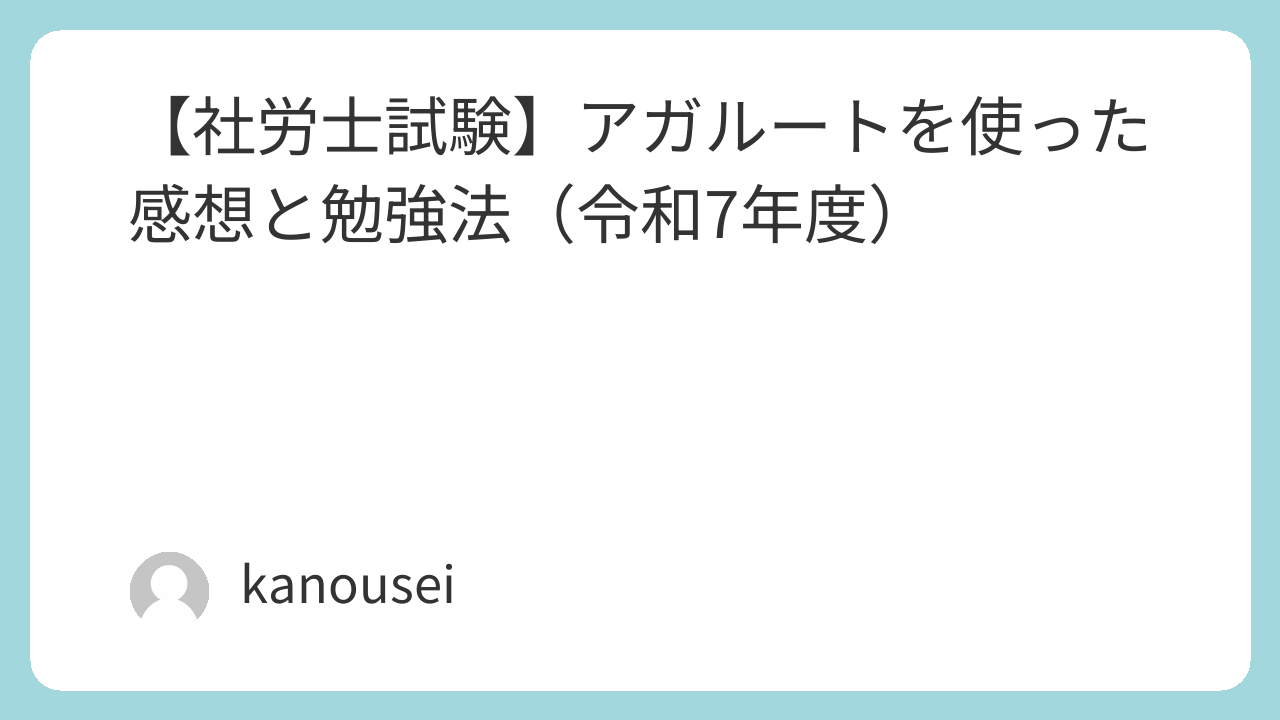
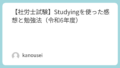
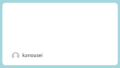
コメント